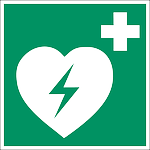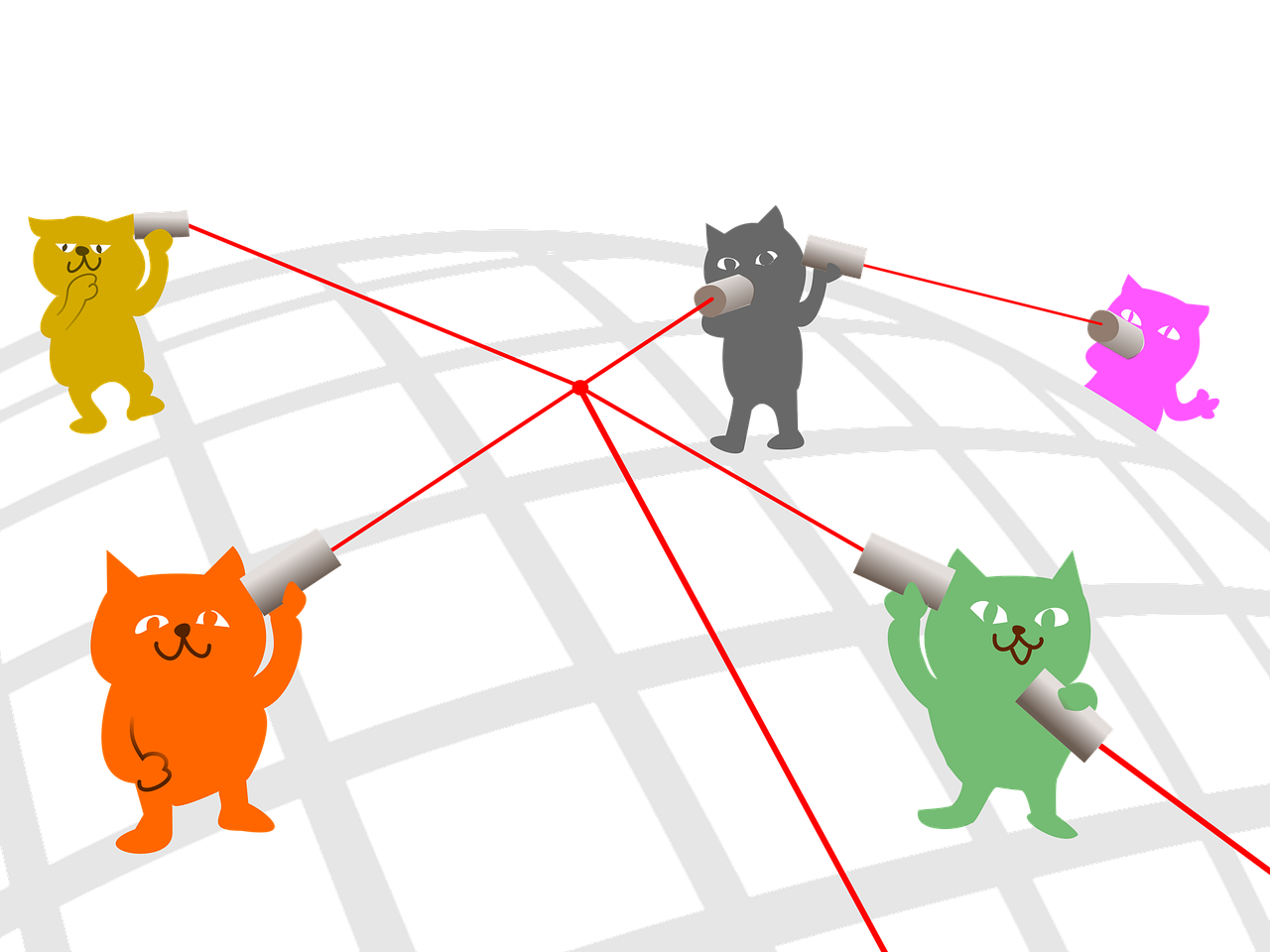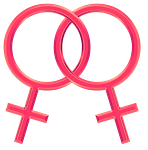
1973年、僕の二十歳の時の恋人〈S〉はバイセクシュアルだった。
僕の恋人〈S〉は高校時代に同級生の女性〈T〉と駆け落ち心中未遂をしていた。
車で死ぬつもりだったらしいが失敗して、その時の傷が体中に幾つか残っている。 特に左の眉毛は斜めにカットしていてそこだけ眉毛が無く、少し怖い印象を相手に与えていた。ふたりは高校を卒業すると、人生の再出発のため島根の浜田市から大阪に行った。しばらくしてTは勤め先で知り合った男と結婚し、一人になったSは大阪を離れ、東京に出てきた。 僕とSは銀座のコーヒー屋のアルバイト先で知り合った。Sのしゃべるイントネーションと言葉は浜田の港町の荒い言葉に大阪弁が混ざり、切れた眉毛と相まってその強烈な個性に、僕はかなりやられていた。 ある時、Sに「うちの初めての男になってくれへん」と頼まれた。
僕は最初の男に選ばれたことがちょっと誇らしかったが、Sはレズビアンに行き詰まり、ノーマルに挑戦していたのだった。そして互いに気に入った僕たちは、まもなく同棲を始めた。
同棲中、僕に語るべき過去などたいして無かったが、Sは語るべき幾つかの過去を話してくれた。そして、どれほど自分が心中しようとしたTを好きだったか、どほれどTが素晴らしい女だったのかを、寝物語に僕に語って聞かせるのが常だった。そして僕はその話しを聞くのがとても好きだった。Sは僕のことを理解があると喜んだが、僕はSの語るTとの物語を聞くのが楽しかったのだ。
僕たちの同棲のバックグラウンドミュージックは、井上陽水の「傘がない」とポール・モーリアの「シバの女王」だった。
題名は忘れたけど演歌もあって、演歌は苦手なはずなのになぜかその時はその演歌も大好きで、6畳一間の風呂無しトイレ共同のぼろアパートで、安酒を飲みながら二人で一緒になって歌っていた。

毎晩Tの想い出を聞かされているうちに、僕は次第にまだ見ぬTのことを少しずつ好きになりはじめていた。そんな僕をSは察知していたが歓迎もしていた。Tはとてもいい女なのだから好きになるのは当たり前だと言った。でも、僕は密かに後ろめたかった。
その年の夏、僕たちはSの二人の母親に会いに広島と島根に行った。
僕たちはまず実母の暮す広島の家に数日間滞在した。その時のSは少し威張っていた。実母夫婦は遠慮気味に静かに僕たちを迎えた。僕たちは当然のように一つの部屋をあてがわれたので、まだ二十歳になったばかりなのにまるで夫婦になったような気がしてすこし居心地がわるかった。
次にSの継母の怪物(Sは継母を怪物と呼んでいた)に会いに島根のSの生家に行った。Sは今度は少し荒れていた。家族は僕が一緒なので戸惑いつつも歓迎してくれていた。釣りや海岸での花火大会やら、いくつかの光景は鮮明に思い出すことができる。
ある日、SとTがよく歩いていたという浜辺に僕たちは行った。散歩をしながらTのことを話していたら、浜辺の向こうに僕たちに向かって歩いてきているTがいた。
大阪に居るはずのTと東京に居るはずのSが、生まれ故郷の想い出の浜辺で偶然出会ってしまうって、いったいどういうことだろう。
 TとSと僕の3人だけが、そこに居た。
TとSと僕の3人だけが、そこに居た。
混乱していた。
どんな会話があったのか、全く覚えていない。
ただ互いに驚きと戸惑と、SとTとのふたりの間に熱い空気が行き場もなく流れ、そして砂浜と僕等3人の足元を洗う波の音が静かにリフレインしていた。
あまりにも劇的な瞬間は、不意にやってきて何気なく去っていく。
1週間ほど滞在して東京に帰る日、「再会」という名の喫茶店で、僕たちはまた偶然Tに再会した。都合良すぎる偶然と喫茶店の名前にさすがに唖然としたが、現実は出来過ぎた偶然でも何事もなかったかのように受け入れるものらしい。
ある日突然、Tが東京のぼくたちの暮すアパートにやって来た。
TはSと同様にノーマルに生きるために大阪で男との結婚に挑戦していたのだが、一年程で離婚していた。本物のレズビアンだったTは元々無理だった結婚に疲れ果てて、東京にやって来たのだった。Tはちょっと粋なお土産を持ってやって来た。それはTが使うことのなかった訪問販売で買わされた大量の高級コンドームで、Tはすこし恥ずかしそうに、僕たちで使えと言った。なんだか僕は哀しかった。きっとTはとても強く何かを決意し、何かを期待し、とにかく頑張ったんだなと思った。
そして、3人で少しの間だけ一緒に暮らした。でもそのコンドームを使った記憶はない。
その後Sと僕は2年の付き合いに終止符を打ち、別れた。
別れは、修羅場だった。
濃密な2年間は濃密な別れを必要としたのだ。
が、とにかく別れた。
しばらくしてから、僕はどうしてもTのことを忘れることができず、なんと僕は別れたSに相談した。案の定、Sはこんな僕はバカにしたりはしなかった。
僕は、Tに告白した。
そして、きちんと振られた。
当然だ。Tはとてもいい女なのだから。
Tは人間として僕を振り、レズビアンとして僕を振った。
僕は二度振られたらしい。
僕はTにもSにも恥ずかしかった。
僕はよくわかっていなかったのだ。
もしかしたら、大丈夫なんじゃないか、なんて思っていたのだ。
何が大丈夫なのか?
僕はいつも、何だか、何でも、大丈夫なんじゃないか?と思っていたふしがある。
でも大丈夫じゃない事はいくらでもあるものだ。
僕はようやく自分の事や周りの人たちの事や様々な事が見え始めてきていた。
未熟で愚かな僕は、Sと別れたこともすべてを後悔していた。
僕はSとTの間を楽しく泳がさせてもらっていただけなのだろう。
恥ずかしかった。
ずいぶんと間抜けな話だ。
それ以来二人には会っていない。
そして、僕は今でもSとTのことをいい女だったと思っている。