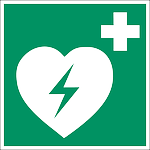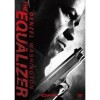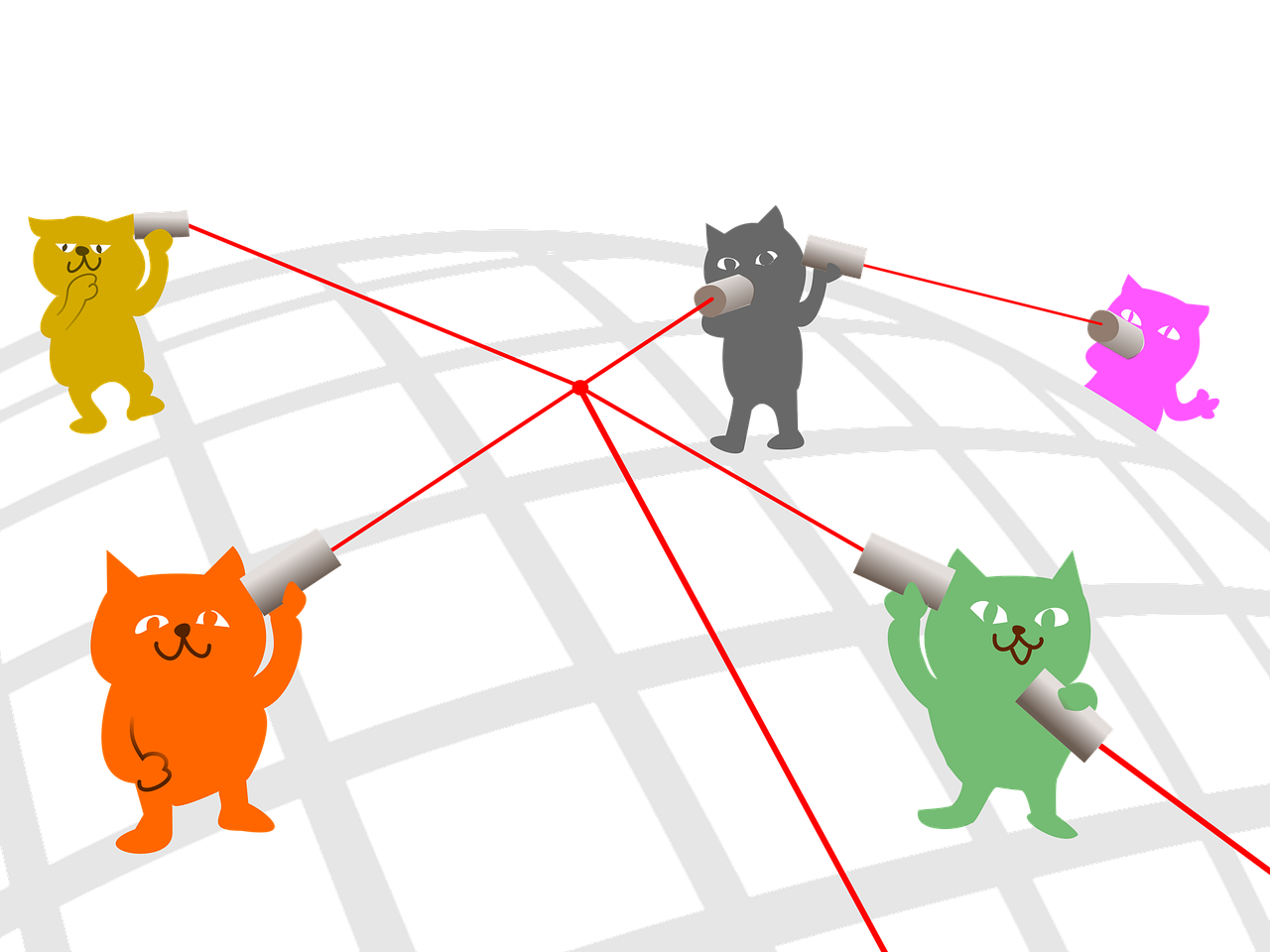陶酔映画の極致
大人になって観るほどに陶酔する映画
若干29才のクロード・ルルーシュ監督が夢想した、大人の世界なのか。
自身がカメラマンとなり、フォトジェニックな映像美の世界に昇華させた。
全く無名の新人がスポンサーもなしに映画史に残る作品を完成させるなんて、ヌーヴェル・ヴァーグというニュー・ウエーブがあったからとも言るが、ルルーシュ独自の世界観の特異性の当然の結果なのかもしれない。
映画製作に於いての行動力はヌーヴェル・ヴァーグ的かもしれないが、当時は日本でさえも体制的な作家として多少の不遇感はあったように記憶してるし、ましてや、本国フランスにおける彼の立ち位置は微妙な息苦しさがあっただろうことは容易にうかがえる。そんな環境の中、まだ無名だったことはむしろ幸運だったのではないか?生涯で一番自分のやりたいようにできた作品だったのかもしれない。
金銭的な制約は自らカメラを担いで極めて短時間に撮ってしまうという、当時では革命的な手法をもたらした。それは軽快なリズムとドキュメンタリーのようなリアル感を生み出すことになった。
更に特筆すべきは、フランシス・レイとクロード・ルルーシュとの出会いである。映像に音楽が効果的に作用するとかではなく、その二つは相互に対等に作用して融合するという、映画史上未だかつてなかったスタイルを生み出したのだ。
幸運で幸福なふたりの出会い
フランシス・レイなくしてルルーシュ作品は成立しないと言ってもいい。
出会いは彼らにとっても幸運だったが、映画界にとっても幸福な出来事だった。これ以降と以前では映像と音楽のかかわり方が明白に違ってくるのだから。
さらに、フランシス・レイのメロディアスでリリカルな音楽性と、ブラジルのボサノバとの融合というチャレンジは、稀に見る成功をもたらした。
そして、アヌーク・エーメの美しすぎるほどの存在が「男と女」の幸運の最後のピースとなり、奇跡の映画が誕生した。
MY評価 : ☆☆☆☆★
1966年公開 フランス 102min
原題/Un homme et une femme (ある男とある女)
監督・脚本・撮影/フランシス・レイ
音楽/クロード・ルルーシュ、バーデン・パウエル
キャスト/ジャン=ルイ・トランティニャン、アヌーク・エーメ、、ピエール・バルー
1966年カンヌ映画祭グランプリ受賞
1966年アカデミー外国映画賞受賞